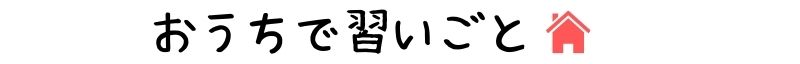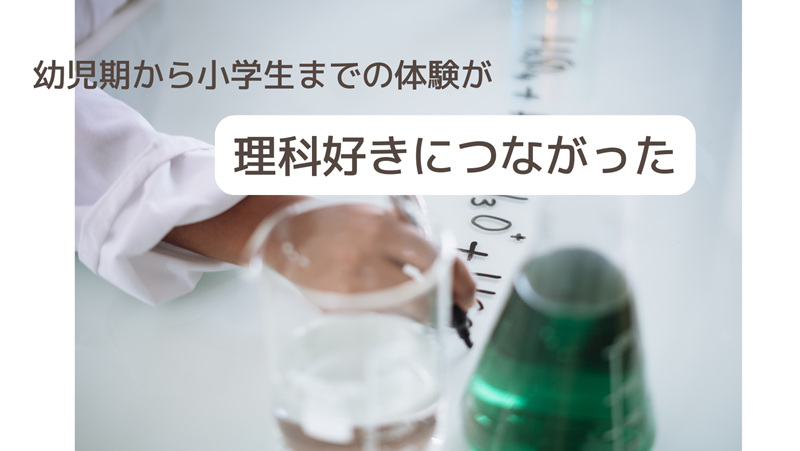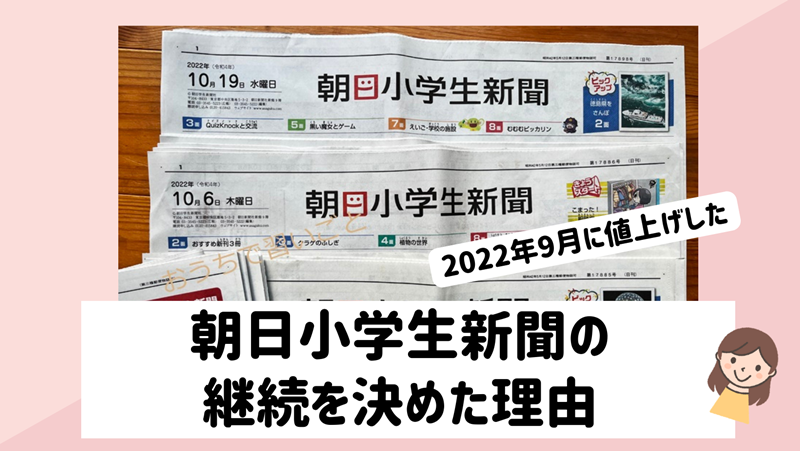「理科好きになってほしい」「苦手な理科を克服してほしい」
先日、模試やテストの結果を塾の先生に提出する機会がありました。
その際、模試やテストの結果を見た塾の先生から「理科女子ですね。どのように理科好きに育てたのですか?」と聞かれました。
今まで考えたこともなかったのですが、昔のことを少し振り返ってみました。
娘は理科が大好きです。
学校で理科の実験が予定されている前日は、まるで遠足の前日のようにワクワクしていることもあります。
ちなみに理科全般得意なわけではなく、苦手な分野もあります。
娘が理科好きなったきっかけが、お子さんに「理科を好きになってほしい」と思われているご家庭のヒントになったらと思い、以下の内容をご紹介させていただきます。
- 幼少期からよく行く場所
- 親がしていること
- 理科好きな娘の特徴
我が家の娘の例ですが、「理科好きになってほしい」「苦手な理科を克服してほしい」と思っているご家庭のヒントになればうれしいです。
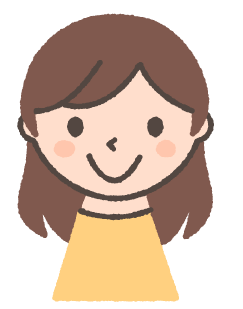
幼少期からよく行く場所、親がしていること、理科好きな娘の特徴の順にご紹介します。
幼少期からよく行く場所
私たち家族が住んでいる地域は自然豊かな環境とはいえない場所です。そのため、日々の生活の中でたくさんの虫や動物とふれあえる環境ではありません。
では色々なところに娘を連れていってあげられたかというと…、あまり連れて行ってあげられなかったと私は思っています。
限られた回数の我が家のレジャーは、娘が小さい頃から自然や動物と触れ合える場所へのお出かけがメインでした。
例えば次のような場所に出かけていました。
- 公園
- キャンプ
- 博物館、科学館、水族館
- 動物園、牧場
「えー、それなら家も行ってたよ!」という声が聞こえてくるようです。
公園や動物園など小さな子のお出かけの定番ですし。
しかし娘の場合は小さな子のお出かけの定番の場所での過ごし方に特徴があるかもしれません。
では、具体的なエピソードとともに子どもがどのように過ごしていたのかをご紹介します。
公園で虫を観察
娘は公園でお友だちと遊具などで遊ぶのではなく、一人で虫や植物を観察していることが多かったです。
虫好きな子がいると、一緒に虫を眺めていたのを思い出します。
例えば、手にいっぱいのダンゴ虫を集めてみたり、アリをじーっと観察したり、チョウチョを追いかけたり、トンボとにらめっこしたり、本当によく虫と遊んでいる子でした。
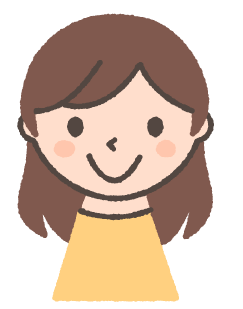
手にいっぱいのダンゴ虫を「はい、どうぞ♪」と笑顔で渡されたときには、悲鳴をあげそうになりました。(苦笑)
キャンプで好奇心に火をつける
キャンプは火起こし、料理、テントやイスなどを組み立てたりと様々な体験ができます。キャンプでの様々な体験は娘の好奇心に火をつけてくれたと思います。
私たち夫婦はどちらかというとアウトドア派ということもあって、年に2、3回キャンプに行っています。
「キャンプは子育てにいい」という話は聞くけれど、虫が苦手だし、道具を揃えるのも大変…。それに準備や片づけも面倒。
その気持ちよくわかります!
キャンプは親にとってハードルが高いレジャーですよね。
キャンプ=テントかというと、そうでもありません。バンガローでもキャビンでもコテージでも大丈夫!
手ぶらキャンプやグランピングなど親の負担が少ないものやママが快適に過ごせそうな方法を選択してもいいと思います。
科学館や水族館は年パスで通いまくる
我が家では、親子(父と娘)で年間パスポートを購入して月に1回以上科学館に通っていました。そして、今年(2022年)は、母と娘で水族館の年パスを買いました!
娘の特徴は、科学館や水族館では興味を示したもの・生物の前から動かないことだと感じています。
また、同じ科学館や水族館に通って「飽きないの?」と思われるかもしれません。
科学館や水族館はワークショップが充実していたり、企画展があったりと毎月通っても飽きないんです。毎回新しい発見があるので我が家では親子で楽しんでいます。
動物を観る・動物とふれあう
娘が小さな頃は「おさるさん、かわいい♪」「リスさん見つけた!」と喜んでいましたが、小学生になると「エゾシカとカモシカの違いは何だ?」という感じで問題を出してくるようになりました。
たまに「えっ!?それどこで知ったの?」というような知識もあって、驚かされます。
そして、動物園や牧場でふれあいができるときは積極的にふれあっています!うさぎの抱っこの仕方、モルモットを抱っこするときに気をつけることなど動物のふれあいで教えていただいたこともたくさんあります。
また、娘が牧場で必ずすることがあるんです。それは、引き馬や乗馬体験です。そのため引き馬がない牧場には行きません。
「ママ、乗馬を習いたい!」と言われた日は、いろんな意味で冷や汗がでました。
こうして振り返ってみると、自然や動物などに触れる場所へのお出かけ、そして少しマニアックな過ごし方!?をしたことが理科好きにつながったのかもしれません。
理科好きな子どもに親がしたこと
理科好きな子どもに親がしたこと
- 観察しているときはひたすら待つ
- 推測した考えを否定しない
- 親も一緒に楽しむ
親がしたことはこの4つくらいです。
観察しているときはひたすら待つ
娘が何かを観察しはじめると長い、長い…。もうそれは何かの!?修行のような時間が経過します。
普段から私が辛抱強いかというと、違います。
日々の生活では「早く着替えなさい!」「早く食べて!」とせかしてばかりです。でもなぜか子どもが真剣なまなざしで熱中している姿を見ると不思議と待つことができるんです。
子どもが推測した考えを否定しない
「こっちのほうが浮くと思うよ」「この昆虫は〇〇の仲間だと思う」「この模様はオスだと思う」など子どもが一生懸命推測したことは否定しないようにしています。
正直に言うと、たまに「それは間違っているような…」と思うこともあります。でも否定はしません。
私が言うことは「どうしてそう思ったの?」と質問をするだけです。
親も一緒に楽しむ
休日の貴重な時間を使ってお出かけするからこそ、親も一緒に楽しんでいます。恥ずかしながら、親が子ども以上に楽しんでいることも少なくありません。
「あまり興味はないけど子どものために我慢しよう…」と親が感じる場所より、親が興味のある場所を選んでお出かけしていいと私は思います。
親が楽しんでいると子どもも楽しそうにしていることが多いのではないでしょうか。
以上、理科好きな子どもに親がしたことを4つご紹介しました。
理科好きな娘の特徴
小学5年になって改めて娘が理科好きだなぁと感じている特徴を5つピックアップしました。
- 昆虫採集が得意
- 自分の中にある知識を使って推測することが好き
- よく星空や月を眺めている
- 実験の前日の夜はワクワクして眠れない
- 夏休みの宿題で一番燃えるのは自由研究!
エピソードを交えながらお伝えします。
昆虫採集が得意
保育園に通っていた頃はなかなか虫を捕まえることができず、親が捕まえていました。しかし小学生になってからメキメキと昆虫採集の腕が上がりました。
「ちょっと公園行ってくるね!」と家を出て10分も経たずに、バッタ5匹、カマキリ3匹、チョウチョ1匹を捕まえてきたことがありました。
小学校高学年の女子が虫取り網を片手に公園で昆虫採集。
なかなか見ない光景ですよねw
昆虫採集が得意だと園児さんから人気があって、「おねえちゃん、見せて」と声をかけてもらえるのがうれしいそうです。
自分の中にある知識を使って生物や植物を推測する
私のスマホには、植物を調べるアプリ「PictureThis」 と 昆虫を調べるアプリ「Biome」をインストールしています。
Picture This >> appleはこちら androidはこちら
Biome >> appleはこちら androidはこちら
娘は見たことがない虫を見つけると、アプリで調べる前にじっくり観察して自分なりの答えを出します。娘は自分の中の知識から推測して答えを出すことが楽しそう。
そんなことを繰り返していると知識が少しずつ蓄積されてくるようです。
よく星空や月を眺めている
「月が幻想的だね」「今日の月はかわいいね」など色々な表現で月の美しさを伝えてくれます。
保育園のお迎えが19時を過ぎることが多かったので、親子で月を眺めながら家に帰ったことも多いです。
実験の前日の夜はワクワクして眠れない
娘は実験が大好きです。
小川のある公園ではペットボトルを使ってろ過の実験をしたり、キャンプ場では燃えやすい葉っぱを探してみたりとできる範囲で実験をしています。
そして学校の理科室で顕微鏡を使う日などはとてもワクワクするみたいで前日の夜から興奮気味です。
困ったことに興奮しすぎて眠れないこともあります。
実験好きな娘の忘れられないエピソードをご紹介します。それは誕生日プレゼントに実験キットやビーカー、リトマス紙をリクエストされたことです。実験グッズが豊富な国立科学博物館のミュージアムショップは一度入ったらなかなか出られません。

誕生日に買ったリトマス試験紙です。
夏休みの宿題で一番燃えるのは自由研究!
夏休みの宿題で娘が一番燃えるのは自由研究です。
夏休みに入る前から、「これもしたい」「あれもしたい」と考えはじめ、夏休みに入る頃には娘が自分で自由研究の内容を決めています。
自由研究は何にするかを決めるまでが大変だと思うのですが、ここだけは楽をさせてもらっています。
ただ自由研究をはじめると、「もう充分」「もうこのあたりで終わってほしい」と親が悲鳴をあげそうになるほど没頭します。娘は深く深く掘り下げていくタイプです。
自由研究の没頭する分、他の宿題になかなか手をつけられないので困っています。
まとめ
今回塾の先生に理科好きに育ったきっかけについて質問があったので、過去のことを振り返ってみました。そこで我が家のレジャーは自然に触れ合うことがメインということに気づきました。
公園や動物園など小さな子どもたちの定番の場所へのお出かけが多かったのですが、娘はその場所で少し!?ときにはかなり!?マニアックな過ごし方をしていたと思います。
理科好きへの道は子どもの頃の体験が大切だということに気づかされました。
親である私特別なことはしていません。ただ親も一緒にとことん楽しんだことは、もしかして娘の理科好きに少しだけ影響したかもしれないです。
お子さんを理科好きに育てたいと思ったら、自然や生物と触れ合える場所で且つ親が楽しめそうな場所に行ってみるのはいかがでしょうか。